2025年8月27日 |
コラム
K-ABC-IIとは?子どもの認知スタイルや学習方法の得意・不得意を把握
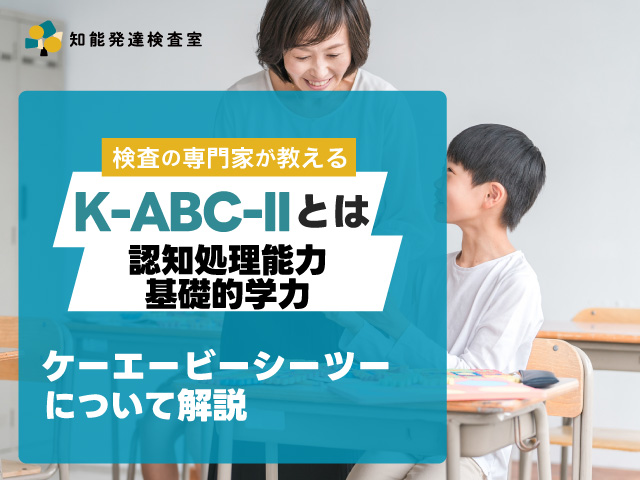
K-ABC-II(Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition)は、子どもの知的能力と学力の基礎となる認知処理能力を多角的に評価するための個別式心理検査です。従来の知能検査とは異なり、子どもの認知スタイルや学習方法の得意・不得意を把握することに重点を置いています。
K-ABC-IIは、2歳6ヶ月から18歳11ヶ月までの子どもを対象とした知能検査です。この検査は、脳の働きを基盤としたカウフマンモデルという理論に基づいており、認知能力を「継次処理」と「同時処理」という2つの側面から捉えます。
継次処理: 音や形などを順番に一つずつ処理する能力です。例えば、指示された順に単語を繰り返したり、文章を読んで理解したりする力に関わります。
同時処理: 情報を全体的に捉え、部分間の関係性を把握する能力です。例えば、パズルを完成させたり、図形のパターンを理解したりする力に関わります。
これらに加え、言語能力や学習能力、計画能力なども測定し、子どもの認知的な強み(得意なこと)と弱み(苦手なこと)を客観的な数値で示します。検査は、専門家(臨床心理士など)と子どもが1対1で行い、パズルや積み木、絵の提示など、子どもの興味を引きやすい課題が多く含まれています。
K-ABC-IIを受けるべき理由
・学術的な理由
K-ABC-IIは、子どもの認知特性を詳細に分析できるため、教育的な支援や指導方法を検討する上で非常に有効な情報を提供します。
得意な学習スタイル(認知スタイル)の発見: 継次処理が得意な子には順を追ったスモールステップでの指導が、同時処理が得意な子には全体像を示してから詳細に入る指導が効果的であるなど、その子に合った学習方法を見つける手がかりになります。
学習のつまずきの原因分析: 例えば、「国語は得意だが算数の図形問題が苦手」という場合、同時処理能力に課題がある可能性が示唆されます。このように、単に「できない」で終わらせず、その背景にある認知的な要因を探ることができます。
・臨床的な理由
医療や福祉の領域では、発達障害の診断補助や支援計画の立案に活用されます。
発達障害の特性理解: LD(学習障害/限局性学習症)やADHD(注意欠如・多動症)、自閉スペクトラム症(ASD)などの子どもは、認知能力に得意・不得意の差(ディスクレパンシー)が見られることが多くあります。K-ABC-IIはその凹凸パターンを明確にし、診断や個々の特性理解の一助となります。
客観的な評価: 保護者や教師の主観的な評価だけでなく、標準化された検査によって子どもの状態を客観的に示すことができます。これにより、関係者間での共通理解が深まり、一貫した支援を提供しやすくなります。
K-ABC-IIで分かること
K-ABC-IIを受けることで、以下のような点が明らかになります。
・総合的な知的能力(知的発達の水準): 同年齢の子どもと比較して、全体的にどの程度の知的能力を持っているかが分かります。
・認知能力の得意・不得意: 「継次処理」「同時処理」「学習能力」「計画能力」などの各指標から、子どもの認知的な強みと弱みが具体的に分かります。例えば、「耳で聞いた情報を順番に覚えるのは得意だが、目で見た図形を理解するのは苦手」といった詳細なプロフィールが把握できます。
・知識や言語能力の発達度: 家庭や学校で学んだ知識がどの程度身についているか、また言葉を理解し、表現する力がどの程度かを評価します。
・学力との関連性: 読み書きや算数などの基礎的な学力と認知能力との関連性を分析し、学習のつまずきの原因を探る手がかりを得られます。
受けることで対策できること
検査結果は、子どもの可能性を最大限に引き出すための具体的な対策や支援に繋がります。
・個別最適な学習計画の立案: 検査で明らかになった認知の強みを活かし、弱みを補うような学習方法を計画できます。
例: 同時処理が苦手な子には、文章題を図やイラストで示して全体像を掴みやすくする。継次処理が苦手な子には、指示を短く区切って伝えたり、手順をリスト化して視覚的に示したりする。
・具体的な支援の要求: 学校の先生や専門機関(通級指導教室、療育センターなど)に検査結果を提示することで、子どもの特性に基づいた具体的な配慮や支援(合理的配慮)を依頼しやすくなります。
・自己理解の促進: ある程度年齢が高い子どもの場合、検査結果を通じて自分自身の得意・不得意を客観的に理解することができます。これにより、自分に合った勉強法を見つけたり、将来の進路を考えたりするきっかけにもなります。
・関わり方のヒント: 保護者や支援者が子どもの「なぜできないのか」を理解し、叱るのではなく、その子の特性に合わせたサポートをするためのヒントが得られます。これにより、親子の信頼関係が深まることも期待できます。
K-ABC-IIは、単に子どもの知能指数(IQ)を測るだけでなく、その子が持つユニークな認知のあり方を理解し、より良い学びや生活に繋げるための羅針盤のような役割を果たす検査と言えるでしょう。
臨床心理士 / 公認心理師 井上 操
